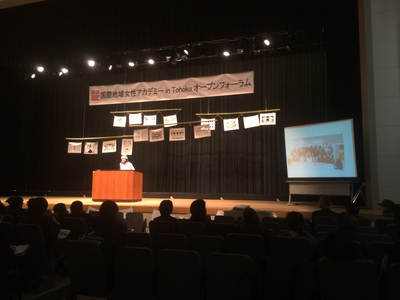
同時に、政府間の協議の裏でも、全国各地でNPO/NGO/企業や市民団体を中心に数多くの防災に関するプログラムが実施されました。
その中に、女性の視点を防災の取り組みの中に入れていこうという「国際地域女性アカデミーinTohoku」というプログラムがあります。
このプログラムは、災害に強いしなやかな地域社会づくりのため、東北と海外から復興や防災の活動に携わる女性たちが30名ほど集い、体験や知恵を共有し、市民社会側からの行動を提案することを目的としています。
2月に東北(岩手、宮城、福島)で活躍する女性達が仙台で合宿形式で各々の取り組みや人となりを理解し合い3月の本番に向けた話し合いを行いしっかりと準備を整え、3月には2日間をかけて海外からの女性リーダーと東北の女性リーダー達とで親睦を深めたり、お互いの取り組みを学び合い、地域や国を越えた今後の女性の視点を入れた防災について語り合いました。
わたくしは微力ながら女性アカデミーの実行委員として、当プログラムに参加者する女性リーダー候補を紹介をさせて頂き、JCNとしても「後援」という形で応援しました。
3月12日(木)の最終日には、プログラムの成果を発表する「オープンフォーラム」が南三陸町ベイサイドアリーナで開催され2月、3月で行われたプログラムの成果発表と、登壇者と会場に集まった全員が「わたしコミット(災害時にわたし、家族、地域を守るために今できること)」を連防災世界会議に向けてアピールしました。
当日は、このプログラムを牽引してきたウィメンズアイ代表の石本さんの強い想いに突き動かされて、フィギアスケート安藤美姫さんや堂本暁子さん、南三陸町の佐藤仁町長もゲストとして会場に駆け付け、プログラムに参加した東北3県と海外の女性達と一緒に防災について対話し、最後に「わたしのコミット(災害時にわたし、家族、地域を守るために今できること)」を宣言しました。このメッセージは南三陸町の中学生から国連防災会議に出席する人たちに託され閉会しました。
いまだに日本社会全体が「男性の視点」を中心に動いている中で、とくに防災の世界はジェンダーバランスが悪いと言われる中で、プログラムの内容も去ることながら、社会へのアピールという意味でもとても重要な会議であったと強く感じました。
このプログラムに関わらせて頂いたことをこの場をお借りして関係者一同に感謝申し上げます。
文責/池座剛
---
国際地域女性アカデミー http://watohoku.com/
ウィメンズアイ http://womenseye.net/
---

こんにちは、岩手の中野です!
岩手は広い。まあ広いです。私は大船渡市というところに住んでいまして、岩手県沿岸の南部に位置するのですが、今回訪れたのはこちら野田村。沿岸の北部に位置するところです。車だと大船渡市から4時間といったところでしょうか。
そんな野田村も津波により甚大な被害を受けましたが、さまざまな人や団体が立ち上がっております。
「NPO法人のんのりのだ物語」は、体験と交流から野田村の活性を目指す団体です。写真はなかなかの山奥にある事務所で、この中がまた素敵な空間になっているのです!
素敵な空間、活動、人、まち。野田村、かなりアツイです。
文責/中野圭
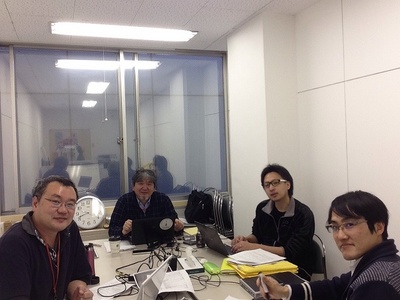
お世話になってます。福島担当、鈴木亮です。
3/24~25に宮城県仙台市にてJCN被災地駐在員ロングミーティングを開催しました。
国連防災世界会議も終わり、2014年度の最後のケース検討会議に合わせての開催で、岩手、宮城、福島の3担当と統括の4人で約8時間、今年度の振り返りと次年度に向けたブレストを行いました。
個人的な所感ですが、2012年9月から福島担当になり、少しでも俯瞰的、課題解決型の視点をもって団体訪問に力を割いてきた結果、中間支援組織間の連携分担が進み、現場のNPOに役立つ動きをできてきたのかなと感じた1年でした。
いつも悩みや失敗はつきませんが、色々お声掛けをいただけたり、支援要請の手をあげていただけたりすることも増え、5年目も頑張らねば、と心新たに新年度に臨みたいと思います。
以下は議論のメモです。
【2014年度振り返り】
【2015年度の向けて】
危機感を失わず笑顔も忘れず、これからもひと鍬ひと鍬耕すように、復興に取り組んでいきたいと思います。
文責/鈴木亮

皆様、こんにちわ!
宮城担当:三浦です。
3月20日(金)名取市被災者支援連絡会に参加しました。
今回で10回を迎えた連絡会は、被災者に今、必要なを考える機会や支援の重複が起きないようにと支援者の情報共有と交流の場として名取市が開催しています。
応急仮設住宅で起きる課題に備えるための勉強会や被災者に必要な支援を考える支援者連絡会は、支援者がこれから取り組む課題に名取市が講師を招くなどして場を提供するなどしている行政と支援団体の協働の連絡会です。

名取市は閖上地区に住居を希望する役400世帯あり、かさ上げ工事などの都合で、平成30年まで仮設住宅で暮らせなくてはなりません。
仮設住宅での生活が長くなり目標が失いがちになってしまうことがないように、名取市被災者支援者連絡会は被災者に希望と生きがいを見つけてもらい、「自立」を促す支援に取り組んでいます。
文責/三浦

こんにちは!岩手の中野です。
先日開催された現地会議には報告しきれなかった話がありました。今回会議の中で、岩手では初めて「ケーススタディ」を取り入れてみたのです。内容は秘密(?)にしておきますが、「民泊事業に関わる民家を増やすには?」「古民家を活用してどう外国人を呼び込む?」など具体的なケースについて参加者から多彩なアイディアが出されました。
実際にこのケーススタディを通じて出されたアイディアが、カタチになっていくプロジェクトも進行しているようです。被災地の今を共有し、伝え、つながり、次の一歩へ。2011年当初から継続してきた現地会議は、少しずつですが確実に進化しています。
文責/中野圭