
事務局の岡坂です。
お盆も終わり、高校野球も終わりました。子どもさんの夏休みも秒読みですね。あ、最近(齢四十を前にして)メガネをやめてコンタクトにしました。感想?うーん視界がクリアになって奥行きがよく分かるようになりました。「今までの20数年間はいったいなんだったんだ。」という気分です。目元をクリアにすると色んなモノがみえてくるようになり、昨日、我が家の前の道路になぜかトランプの「ダイヤのエース」が落ちていました。これはいったい何のお告げなんだ...。
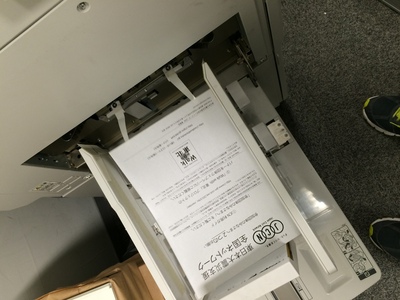
さて、きょうは主にJCNの参加団体さん向けのお知らせです。先週末辺りからJCNの活動報告書と計画書を皆さんにメール便で送っています。現物をお送りする機会はあまりありませんので、「東北応援ビレッジ」の報告書や「避難されている方々へ」のチラシなど同封しました。
A4、1枚ですが、登録情報の確認の紙を入れています。これ必ず目を通して頂いて、(特に総会でご連絡をいただいてない会員団体さま、それから協力団体さま)はFAXで返信ください。
それから「Walk with 東北」プロジェクトへご協力のお願いも同封しています。こちらを参考にぜひみなさんの団体のウェブページにバナーを貼ってください。(冒頭が上野動物園のパンダですみません。)
諸々ありますが、今回も岡坂が精魂込めてお返事がくるようにおつくりした書類です。ぜひみなさんの目にとまり、お読みいただけますように。
文責/岡坂 建
訪問先:一般社団法人三陸ひとつなぎ自然学校
訪問日:2014年7月16日
取材者:中野圭
こんにちは、岩手の中野です!
今回は岩手県釜石市で活動する三陸ひとつなぎ自然学校の伊藤さんにお話をお聞きしました。
―― Q.取り組んでいる地域課題は?

最大の課題は地域における人材や担い手の不足。震災直後は単純にやらなければいけないことが目の前にいっぱいあるが、地域に人がいないという状況だった。だから外部のボランティアが求められたし、足りない人材を外部で補うという形だった。現在では徐々に地域の中で「あれやりたい」という想いが芽生えてきている。しかしながらやはり人材・担い手は不足している。だからこそ地域の前向きな「やりたい」という思いを実現するために、外部人材の活用が必要となる。
もう一方で、こどもたちの居場所が減ったことは確かである。遊ぶ場所や放課後の居場所など、震災の影響で少なからず環境も変わり、どうしても居場所が減ってしまっている。ただ、本来は自然そのものが遊び場になるということを忘れてはいけない。子どものうちに、自分の地域のいいところをできるだけ多く知ってもらいたい。高校を出て一度は地元を離れても、いつか戻ってきたいと思えるように地域のいいところをたくさん見せておきたい。 この地域がこれからも持続可能であるために、「外部人材」が「今」求められているもの、「こども」が「未来」に求められるものである。
―― Q.どのような取り組みをされているのですか?
基本的には3つの取り組みを行っている。まずひとつがエコツアーの実施。1泊~9泊くらいまで取り扱う。地域のやりたいことを実現するお手伝いをしていく。2~3人から、バス2台ぐらいまでの受け入れ体制の中で、観光に近いものから大学生のスタディツアー、企業の研修など多様である。
もうひとつはこどもの居場所づくり。放課後子ども教室は平日週3回行っており、外で遊ぶことが多い。森を借りて遊び場をこどもたちと一緒に整備している他、キャンプを通じて地域のいいところを発見する機会の提供も行う。
そしてもうひとつがボランティアやインターンコーディネート。これからはボランティアの減少に伴い、インターンに移行していこうと思っている。地域側にあるニーズをしっかり拾って、インターンとともに具体的に実践しながらこれから作り上げていく。
―― Q.どの様なメンバーで取り組まれているのでしょうか?
団体には4人が常勤。加えて釜援隊から1人。長期ボランティアは2週間から1ヶ月くらいが多い。常時1?3名くらいが平均的で、夏休み等は10名くらい。一方ツアーのほうは年間800人から1000名くらい。
―― Q.困っていることはありますか?
組織としては、拠点を整備したい。地域の使っていない保育所を借りて使っているが、しっかりとした拠点があれば運営や活動も推進する。地域的には、「人材不足」「こども」が大きなテーマであることには変わらないが、加えて「自然環境」の保全は今のままでいいのだろうか。復興はハードが中心になるのはもちろん仕方がないこと。生活再建ももちろん大事でありつつも、この豊かな自然・環境に配慮することが求められる。後世に残していかなくてはいけないものも確かに存在する。
―― Q.復興を応援してくれる人達にお願いしたいこと、伝えたいことはありますか?
一言であらわせば「来てほしい」。いまだに被災地に行っていいのかという思いを抱えている人もいるようだが、地域での受け入れ体制もできている。この地域でまだまだ頑張って、もがいている人もたくさんいる。まずは来て、見て欲しい。そしてこの東北全体が、語弊を恐れずに言えば、課題先進地であるだけに、社会実験そのものであり、その中に参加するということもまた、日本人として、大切な機会になるはずだから。
<了>
【関連情報】
(URL)http://www.fukko-todai.com/santsuna/
【問い合わせ先】
この記事への問い合わせは、JCNまで。お問合せ
訪問先:NPO法人いわて地域づくり支援センター
訪問日:2014年7月26日
取材者:中野圭
こんにちは、岩手の中野です!
今回は岩手県大船渡市崎浜(さきはま)地区で活動するいわて地域づくり支援センターの若菜さんにお話をお聞きしました。
―― Q.取り組んでいる地域課題は?

崎浜地区は被災した約200世帯くらいの集落で、被災した人たちの住宅再建支援含め集団移転事業の支援をおこなっている。およそ22世帯が移転、公営住宅7世帯ほど。海に突き出た半島部に位置するすり鉢状の集落で地形的にもまとまっており、仮設団地は地区内に設置され、集団移転団地に移る人ももともとの地域の人たちだけであるため、この地域ではコミュニティの課題はないといっていい。そういう意味ではひとつの理想的な事例として提案できるかもしれない。
また、集団移転事業とは別の取り組みとして、浸水した土地利用の構想を描く支援もおこなっているが、将来の土地利用や集落のあり方を描くにあたって、地域の復興会議には若者の参加が少なく、本当の意味で将来的な姿をなかなか描きづらいという問題に直面している。また、これから描いた絵を実現させるに当たっては、地権者との交渉や、関係者の調整などこれからも多くの問題や課題が発生する見込みである。
―― Q.どのような取り組みをされているのですか?
集団移転事業は、国の支援を受けて行政が造成等をおこなうが、移転先団地をどこに設置するか、道路・宅地の配置をどうするかなどは行政と住民が一緒にやらなければならない。崎浜の場合は被災者連絡協議会として被災者の組織化ができていた。私たちの団体としては協議会内部の意見集約のお手伝いができたと思う。丁寧に意見を吸い上げるところから始められたので、住民が最初から計画に入れたという意識ができたと思う。団体としては当初単に住宅再建支援として、復興住宅の視察や情報提供、個別相談をおこなっていた。個々に寄り添う支援と集団移転団地の協働の取り組みをサポートするという主に2つのことをおこなっている。
また何か困りごとがあっても周囲に相談しないという地域性がある。そこで外部が入って丁寧に困りごとを聞くことが必要とされていると感じている。
―― Q.困っていることはありますか?
やはり造成工事が進まない。沿岸部では資材不足、人手不足が深刻。さらに実際に移転地が造成された後も家を建てられるかは個人の問題になる。それぞれの人が実際にたてられるかどうかは一人ひとりにきいてみないとわからない。今後住民向けにアンケートを実施する予定。施工業者がみつかったかなどを丁寧に聞き取り個別の困りごとに対応したいと思う。
一方で若者と年寄りの分断もあると感じる。働き方が昔と今では違う。昔はみんな漁業という時代だったが今は違う。市街地への勤め人が多い。そうした多様な人たちが理解しあいともに地域づくりを考えられる場を考えていかなければならない。
―― Q.復興を応援してくれる人達にお願いしたいこと、伝えたいことはありますか?
これから復興をどうしていくかというのは、そもそもこれからこの地域をどうしていくかという全国の農山漁村、一次産業の問題に取り組もうとしているのと同じであると感じる。「震災の問題」として取り組むことには限界があるので、この地域をどうするかという覚悟をもって住民とともに取り組まなければならない。全国の人たちには、日本の農山漁村との関わりあい方、一次産業との関わりあい方を見直すところから意識して、その価値を考えてみてほしい。
<了>
【関連情報】
(URL)http://iwa-c.net/
【問い合わせ先】
この記事への問い合わせは、JCNまで。お問合せ