「考える」 「関わる」 |
| タイトル | 3.11の今がわかる会議2022 |
|---|---|
| 開催日時 | テーマ1:地域コミュニティの現在地 〜11年目の現状と課題〜 テーマ2:復興まちづくりの現在地 〜11年目の現状と課題〜 |
| 参加方法 | オンライン(Zoom)による参加 |
| 参加対象 | 東日本大震災に関心のある方/東北に関わりを持たれたい方 |
| 参加費 | 無料 |
| 主催 | 東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN) |
| 協力 | NPO法人 いわて連携復興センター 一般社団法人 みやぎ連携復興センター 一般社団法人 ふくしま連携復興センター 一般社団法人 みちのく復興・地域デザインセンター |
| 助成 | 復興庁コーディネート事業 |
震災から11年が経過した被災地の地域コミュニティは、住民が帰還しコミュニティ形成をこれから始めるところ、様々な支援が入りながらもコミュニティが形成されていないところ、形成されたコミュニティが解散してしまったところ、コミュニティの運営を持続可能な体制へ転換するフェーズにきているところなど一様ではありません。震災でゼロから始まった地域コミュニティづくりの現状と課題を、岩手、宮城、福島の現場の方からお聞きします。
 |
岩手:黄川田美和氏 「地域づくり」「まちづくり」に関わる活動をしています。この分野に足を踏み入れることになったきっかけは、東日本大震災でした。職を失い市の臨時職員を1年間務める中で、中間支援という言葉は知りませんでしたが必要性を感じ「地域づくり」「まちづくり」は「誰かがやってくれるもの」ではない事に気付き今があります。 |
 |
岩手:大和田智一氏 陸前高田市生まれ、立正大学を卒業後、関東で生活をしていたが、震災を機に帰郷。帰郷後、障がい福祉事業所へ勤務し、障がい福祉分野の復興事業等へ携わる。その後、障がい者の就労支援等に従事。2019年より現職。陸前高田市の市営住宅管理業務を行っている。 |
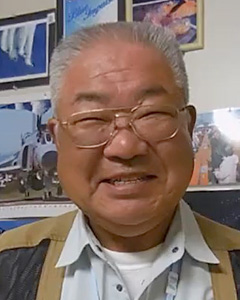 |
宮城:小野竹一氏 震災により東松島市大曲浜地区の自宅を失う。矢本運動公園西地区の自治会長となり、笑顔や元気を取り戻せるコミュニティづくりに奮闘。2014年5月より東松島市あおい地区まちづくり整備協議会会長として、防災集団移転のおける住民同士の話し合いを進める。2016年4月にあおい地区内の3つの自治会を横断する組織、あおい地区会を設立し、会長となる。 |
 |
福島:池崎 悟氏 福島県双葉郡浪江町出身。町内で自動車整備工場を経営し生計をたてるも、震災による全町避難となり事業継続を断念。生活の為、2011年5月に浪江町役場臨時職員となり、8月から当初は雇用創生の一環でもある生活支援相談員として社会福祉協議会へ。臨時から常勤を経て、2013年に正規職員となり現在に至る。 |
東日本大震災から11年目が経過し、被災地では人口減少、高齢化、若者の減少による担い手不足や基幹産業衰退、関係人口の創出、地域活力の発掘などまちづくりにおいてさまざまな課題が挙げられており、まちの賑わいを取り戻すために一からまちづくりに取り組む地域も多くあります。復興から今、そして将来のまちづくりに取り組む方々に被災地の今の現状をお話いただき、皆様と一緒に考えていきたいと思います。
 |
岩手:古谷恵一氏 神奈川県横浜市出身。所属していた大学のアカペラサークルの活動で、震災前2008年から陸前高田市を訪問。震災後は、関東の教育会社にて約5年間働きながら定期的に同市を訪れ、「もっと陸前高田のことを知りたい、もっとたくさん人にも知って欲しい」という思いが強くなり移住。現在は、観光や研修の受入れを行う仕事に従事。 |
 |
宮城:高橋由佳氏 精神保健福祉士・職場適応援助者(ジョブコーチ)、日本ファンドレイジング協会准認定ファンドレイザー。2011年、こころの病を持つ人たちの就労・就学支援を行うNPO法人Switchを設立。16 年には、「ソーシャルファーム」を理念とした就農支援の同法人を設立し、石巻市北上町で農業の担い手育成を行う。また2022年7月より石巻市内にブルワリー(イシノマキホップワークス)をスタートした。 |
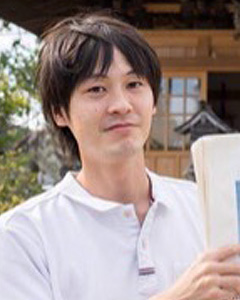 |
福島:山根辰洋氏 東京都出⾝。東⽇本⼤震災をきっかけに2013年双葉町に委嘱職員として参画。2016年に双葉町民と結婚し、支援者から地域を創る当事者として、生業(人生)を通じた地域再生を目指し独立。2019年、観光産業、交流・関係人口創出を通じた地域再生を目指す、⼀般社団法⼈双葉郡地域観光研究協会(F-ATRAs)を設⽴。双葉町議会議員も務める。 |
※テーマ1、2共通
申込フォームからお申込みください。
(※複数名で申し込まれる場合は、お手数ですが、お一人ずつお申込みください)
東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN)事務局
Tel. 03-3277-3636
メール: office@jpn-civil.net
|
災害時、子どもが考えていたことや感じていたことをどこまで知っていますか。 2019年度より開催した3.11ユースダイアログでは、若者から多くのことが語られました。3.11ユースサミットでは語られた言葉から、今、私たちが考えるべきテーマについて、若者と一緒に対話します。
|
◎開会:開会挨拶/趣旨説明
◎1部:テーマについて登壇者同士の対話
◎2部:テーマについて参加者と登壇者の対話
◎3部:登壇者からのメッセージ
◎閉会:総括/閉会挨拶
東日本大震災を経験された若者8名、中越地震を子どもの頃に経験された方、阪神・淡路大地震を経験された方1名が登壇します。
阿部 愛さん
宮城県石巻市渡波地区出身、在住。発災時は幼稚園年長(6歳)。幼稚園の親しい友人を亡くし、「友人の分まで生きてほしい」という友人の祖母からの言葉で、自分を鼓舞して生活してきた。クラーク記念国際高等学校で幼児教育やパフォーマンスを学ぶ高校3年生。
志賀風夏さん
川内村出身。東日本大震災時は相馬高校1年生。原発事故による県外への避難経験もある。現在は村に戻り、陶芸家/草野心平記念館管理人として村に関する様々な活動を行っている。今年の秋からコミュニティカフェ秋風舎をオープンさせ運営している。
江刺逸生さん
岩手県大船渡市出身。東日本大震災発生時は、地元の中学校に通っていた。自宅は津波到達地点から数百メートル離れた場所に位置し、ぎりぎりのところで浸水を免れた。地元の高校に進学し卒業した後は、心理学を学ぶために県外の大学へと進んだ。現在は千葉県松戸市在住であり、公認/臨床心理師として病院に勤務している。
清水葉月さん
福島県浪江町出身。高校2年生の時に東日本大震災を経験し、関東へ避難。その後、宮城県女川町・石巻市で放課後の学習支援や子どもの声で運営する児童館の職員など子ども支援に携わる。現在は(一社)Smart Supply Visionで子ども・若者の声を届けるファシリテーターとして活動。震災を語る若者たちのコミュニティの場づくりも行っている。
香月昴飛さん
1993年生、宮城県石巻市出身。高校2年生時、3.11により被災し震災孤児に。翌年、消防士を拝命。現在は教育系IT企業にて、ICT支援員等に従事。今回は孤児であった目線から被災後のサポート体制や復興について考えていけたらと思います。被災時の手記はこちら「https://onl.bz/SfXamvy」
田中彩貴さん
中越地震の発災時は小学校6年生。長岡市の自宅で震度6弱の揺れに見舞われる。地震直後は数日車中泊をしてから小学校で避難所生活を送る。現在はローカルタレントとして活動し、中越防災安全推進機構のスタッフとしても当時の様子を振り返りながら防災について伝えている。
高橋未宇さん
現在23歳。岩手県陸前高田市出身、在住。生まれつきの脳性麻痺による車いすユーザー。当時は小学校5年生。震災から1週間後、盛岡市へ移り、4年間を過ごす。高校入学と同時に帰郷し、現在は福祉施設で働く傍ら、福祉×防災の視点で研究、語り部や研修講師等として発信をしている。
中村 翼さん
1995年1月17日神戸市兵庫区生まれ。27歳。阪神淡路大震災が発生した午前5時46分の約12時間後の午後6時21分 三宮の上田病院にて誕生。神戸市立明親小学校入学後、小学5年生の時に父親の転勤により岐阜県へ移住し、中学3年生まで過ごし、再び神戸へ。神戸市立須佐野中学校卒業後、県立神戸北高校から神戸学院大学に進学し、現在に至る。現在は、兵庫県内で会社員として過ごす。
佐藤勇樹さん
富岡町3.11を語る会語り人。福島市在住。小学5年生の時に富岡町で被災、原発事故によって県外への避難も経験した。福島大学の学生であった一昨年から語り部としての活動を始め、現在は仕事をしながら語り部の活動をしている。
武藤礼司さん
福島県富岡町で小学校3年生の時に被災。福島原発事故の影響により、全町避難となった富岡町から家族とともに佐賀県に避難。高校までを佐賀で過ごし、大学進学と同時に福島市に移り、福島大学で地域づくり学んでいる大学3年生。
| 開催日時 | 2022年12月17日(土)13:00-16:30 |
|---|---|
| 開催方法 | オンライン(Zoom) |
| 参加対象 | 東日本大震災の若者の声の関心ある方(50名・先着順) |
| 参加費 | 無料 |
| 主催 | 東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN) |
| 助成 | 復興庁コーディネート事業 |
| お問合せ | 東日本大震災支援全国ネットワーク 事務局 office@jpn-civil.net Tel: 03-3277-3636 |
お申込み受付は終了いたしました。
震災から11年が経過した今、当時小学生だった若者がどのような体験をし、どのようなことを感じながら人生を過ごしてきたのか生の声を聞くことで、震災を経験した子どもへの理解や接し方をともに考える機会にしたいと考えています。
●東京会場:川田季代さん
福島県南相馬市小高区出身。震災時は小学5年生で、千葉県や東京都、宮城県等で避難生活を送り、新潟の大学に進学・卒業後、地元に戻りました。現在は、小高区のデザイン事務所でアシスタントデザイナーとして働いています。
●愛知会場:久保 翼さん
岩手県釜石市両石町に住んでいます。震災当時は小学1年生でした。震災で家を流され、少しの間花巻市にいました。周りからの支援にすごく助けられました。その後、釜石に戻り仮設住宅に住みました。そこでボランティアの大学生団体と出会い、今でも家族のような関わりが続いています。現在は親の跡継ぎで漁師をしています。
●大阪会場:岩佐優稀子さん
宮城県山元町出身。2001年生まれ。震災当時小学3年生。自宅への津波被害は免れたものの、電気水道のライフラインが寸断され、当時3歳の妹と支援物資の配給に並ぶ生活を経験。現在は山形大学で地域公共政策を専攻。過疎地域における若者や「よそ者」の重要性について学び、地域の再興に貢献することが目標です。
| 開催日時 | 2022年12月4日(日)13:00-16:00 |
|---|---|
| 会場 |
◎東京会場 ◎愛知会場 ◎大阪会場 |
| 参加方法 |
|
| 参加費 | 無料 |
| 主催 | 東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN) |
| 協力 | 立教大学ボランティアセンター、立教大学Frontiers/日本福祉大学 NPO法人レスキューストックヤード/まるっと西日本 |
| 助成 | 復興庁コーディネート事業 |
| お問合せ | 東日本大震災支援全国ネットワーク 事務局 office@jpn-civil.net Tel: 03-3277-3636 |
お申込み受付は終了いたしました。
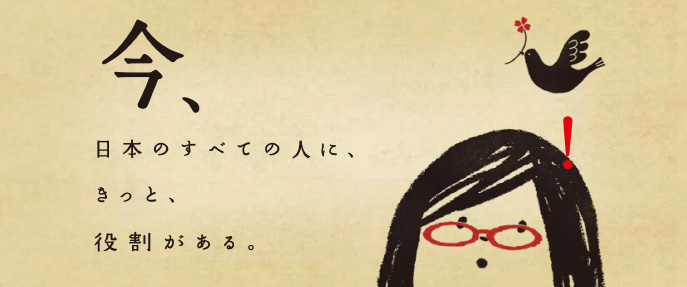
各地域において、避難者の置かれている状況は変化しつつも、コロナ禍において孤立化が進んでいる。避難者支援活動が展開されているが、相談対応・つながりづくり、情報提供などの各種事業は、一部の団体での対応となっている。また、つなぎ先(相談や協力を求める先)が限られている。
地域ごとに避難者支援の制度や体制などの違いもあり、避難が長期化する中で、各地の実情の把握とそれにあわせ、将来を見据えて、地域ごとに地域資源や専門機関等との連携、つなぎをこれまで以上に強化していく必要がある。
そのため、これまで各地で展開してきた取り組み事例を共有し、避難者支援を実施する上で押さえておくべきポイントをあらためて確認する機会とする。さらに、これまでの避難者支援の実例を踏まえて、コミュニティソーシャルワーカー(CSW)の実践をお聞きするとともに、CSWとともに、今後の避難者支援のあり方、方向性を考える機会とする。
第1回
◎日時:令和4年2月10日(木)13:00-17:00
◎開催方法: Zoomによるオンライン開催)
第2回
◎日時:令和4年3月2日(水)13:00-17:00
◎開催方法:新型コロナウイルス感染症の流行状況にあわせてハイブリット開催を想定(会場は東京都内)
これまで避難者支援に関わったことがある民間支援団体
広域避難者支援に関心のある団体、個人
東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN)
福島県「令和3年度県外避難者支援運営業務」の一環で実施
| 1. | 開会(13:00)
開会挨拶、趣旨説明 |
| 2. | 事例報告(13:10) 事例紹介1:個の支援=古部真由美氏(まるっと西日本) 事例紹介2:面の支援=桜井野亜氏(沖縄じゃんがら会) 事例紹介3:組織の支援=森本佳奈氏(愛知県被災者支援センター) |
| 3. | パネルディスカッション(14:30)
パネリスト:
コーディネーター:栗田暢之氏 |
| 4. | 意見交換(16:00) 参加者同士のグループディスカッション |
| 5. | 事務連絡・閉会(16:50) |
| 1. | 開会(13:00)
開会挨拶、趣旨説明 |
| 2. | 話題提供(13:10) 朝比奈ミカ氏(千葉県中核地域生活支援センターがじゅまる所長) 徳弘博国氏(香美市社会福祉協議会事務局長) |
| 3. | パネルディスカッション(14:30)
パネリスト:
コーディネーター:栗田暢之氏 |
| 4. | 意見交換(16:00) 参加者同士のグループディスカッション |
| 5. | 事務連絡・閉会(16:50) |
申込フォームからお申込みください。
(※複数名で申し込まれる場合は、お手数ですが、お一人ずつお申込みください)
東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN)事務局
Tel. 03-3277-3636
メール: kouiki@jpn-civil.net